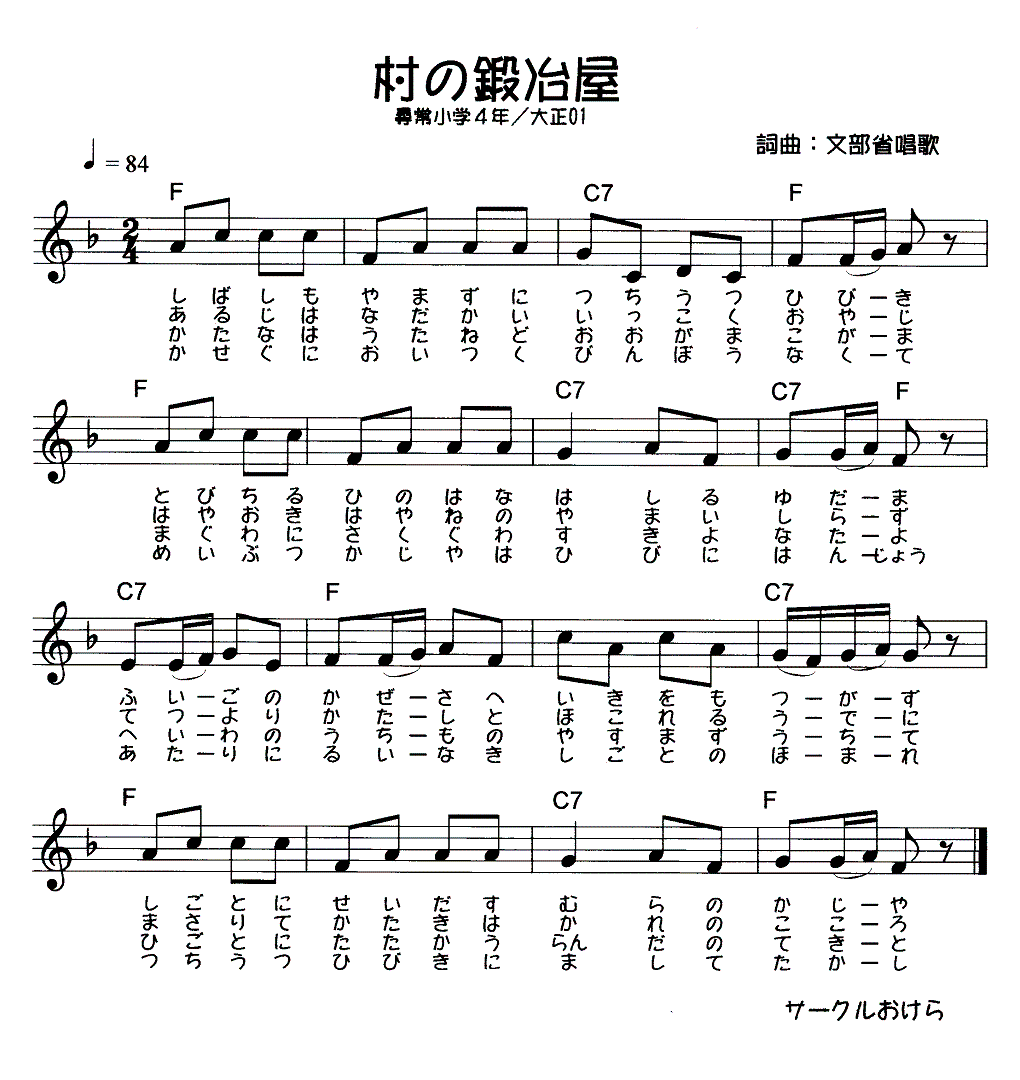村の鍛冶屋(F)
尋常小學唱歌(第四學年)/大正元年
|
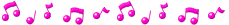  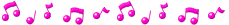 |
作詞
作曲 |
作者不詳 |
 |
1 |
暫時(しばし)もやまずに 槌(つち)うつ響(ひびき)
飛び散る火の花、はしる湯玉(ゆだま)
■鞴(ふいご)の風さえ 息をも継(つ)がず
■仕事に精出す 村の鍛冶屋 |
|
|
| 2 |
あるじは名高き いっこく老爺(おやじ)
早起・早寝の 病(やまい)知らず
鉄より堅(かた)しと ほこれる腕に
■勝(まさ)りて堅きは 彼がこころ |
| 3 |
刀はうたねど、大鎌(おおがま)・小鎌
馬鍬(まぐわ)に作鍬(さくぐわ) 鋤(すき)よ鉈(なた)よ
■平和のうち物 休まずうちて
■日毎に戦う 懶惰(らんだ)の敵と |
| 4 |
かせぐにおいつく 貧乏なくて
名物鍛冶屋は 日日(ひび)に繁昌(はんじょう)
■あたりに類なき 仕事のほまれ
■槌うつ響に まして高し |
|
|
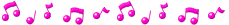  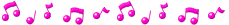 |
|
▼初等科音楽2バージョン |
|
3番以降はCUT! |
| 1 |
しばしも休まず 槌うつ響き
飛び散る火花よ 走る湯玉
■ふいごの風さえ息をもつがず
■仕事に精出す 村の鍛冶屋
|
2 |
あるじは名高い いっこく者よ
早起き早寝の やまい知らず。
■鉄より堅いと 自慢の腕で
■打ち出す刃物(はもの)に 心こもる
|
|
▼昭和22年バージョン |
|
3番以降はCUT! |
| 1 |
しばしも休まず 槌うつ響き
飛び散る火花よ 走る湯玉
■ふいごの風さえ息をもつがず
■仕事に精出す 村の鍛冶屋 |
2 |
あるじは名高い 働き者よ
早起き早寝の やまい知らず
■永年鍛えた 自慢の腕で
■打ち出す鋤鍬(すきくわ) 心こもる |
|
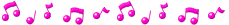  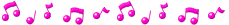

 |
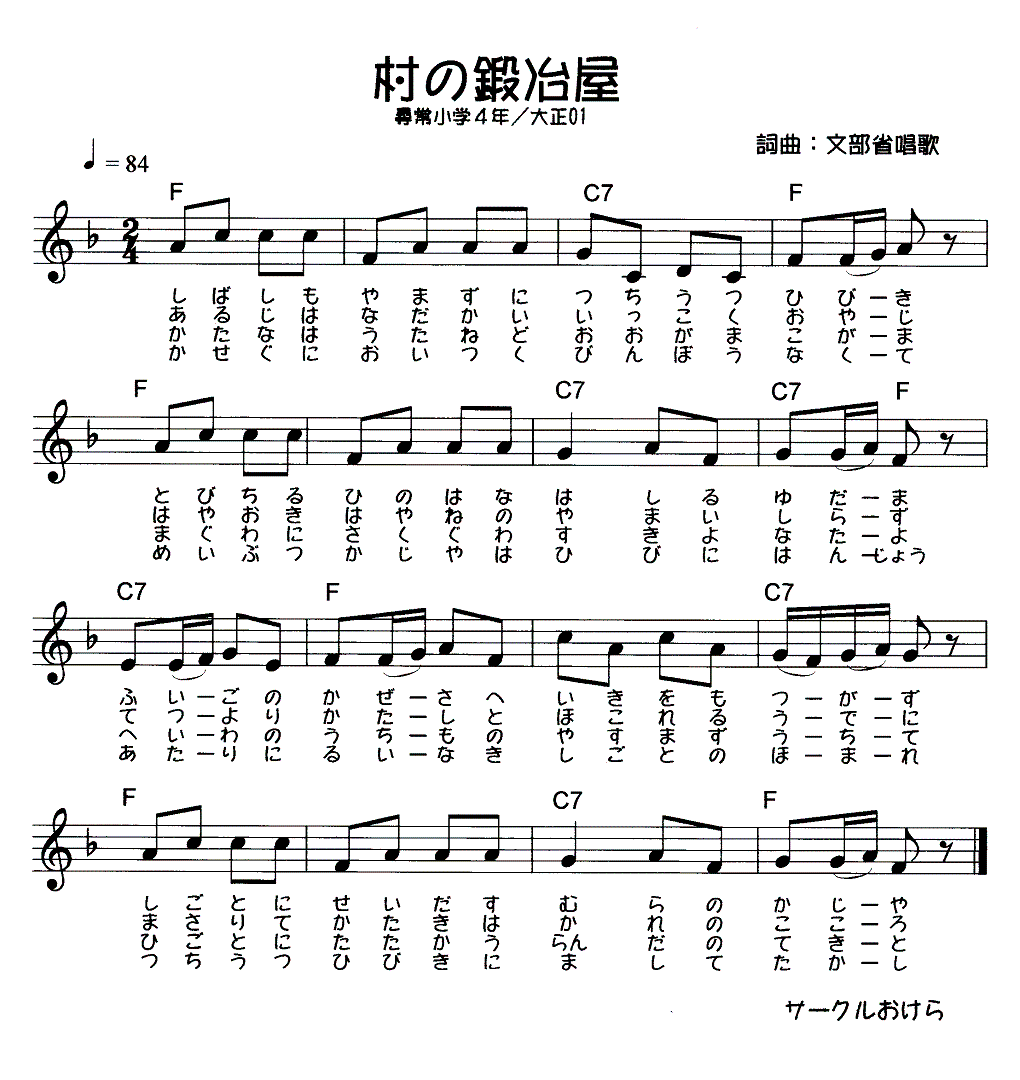
歌詞:08/01/18/midi:08/06/15-12/02/12-12/12/16/楽譜:bunbun(2016/04/16)おけらの唱歌 |
■おやじという俗語が文部唱歌に用いられたのはこの曲だけ。労働讃歌でもある。昭和17年の「初等科音楽2」にも載せられたが、時宜に合わないためか、歌詞は改定され、「おやじ」は消され、かつ第3節以下も削除された。昭和22年「4年生の音楽」にも載ったが、ここでも占領下に合わせて、刃物…の歌詞改定があった。
小学校の教科書には必ず載せる教材だったが、昭和52年、「村」という自治体単位が無くなった県があり、これに伴って「村の鍛冶屋」「村祭」という、村の付く教材は抹消された。
■全国で数県、その単位が無くなっただけで、この歌を抹消することは、はなはだ馬鹿げている。子供達の前で、ひと言説明すればすむことだし、町や市という単位になっても、生活そのものが、変化しているわけではない。人々の生活を無視した机上の論理である。 |
●lunatyさんより、詳細な時代背景の解説をいただいたが、この曲に限らず、唱歌そのものの基本である啓蒙力は、その時代の背景を抜きでは語れないものです。曲の生まれた背景を解説できれば良いのでしょうが、力量不足、資料不足もあり、なかなか思うに任せないのが事実です。
為政者の10年いや100年単位での先を見通す(善し悪しは別として)力量は、決して侮れないと思います。事ここに至ってからひっくり返すのは至難の技。そうした考え方、背景に対し、常々の見極めが大切なのでは無いでしょうか。 |
|